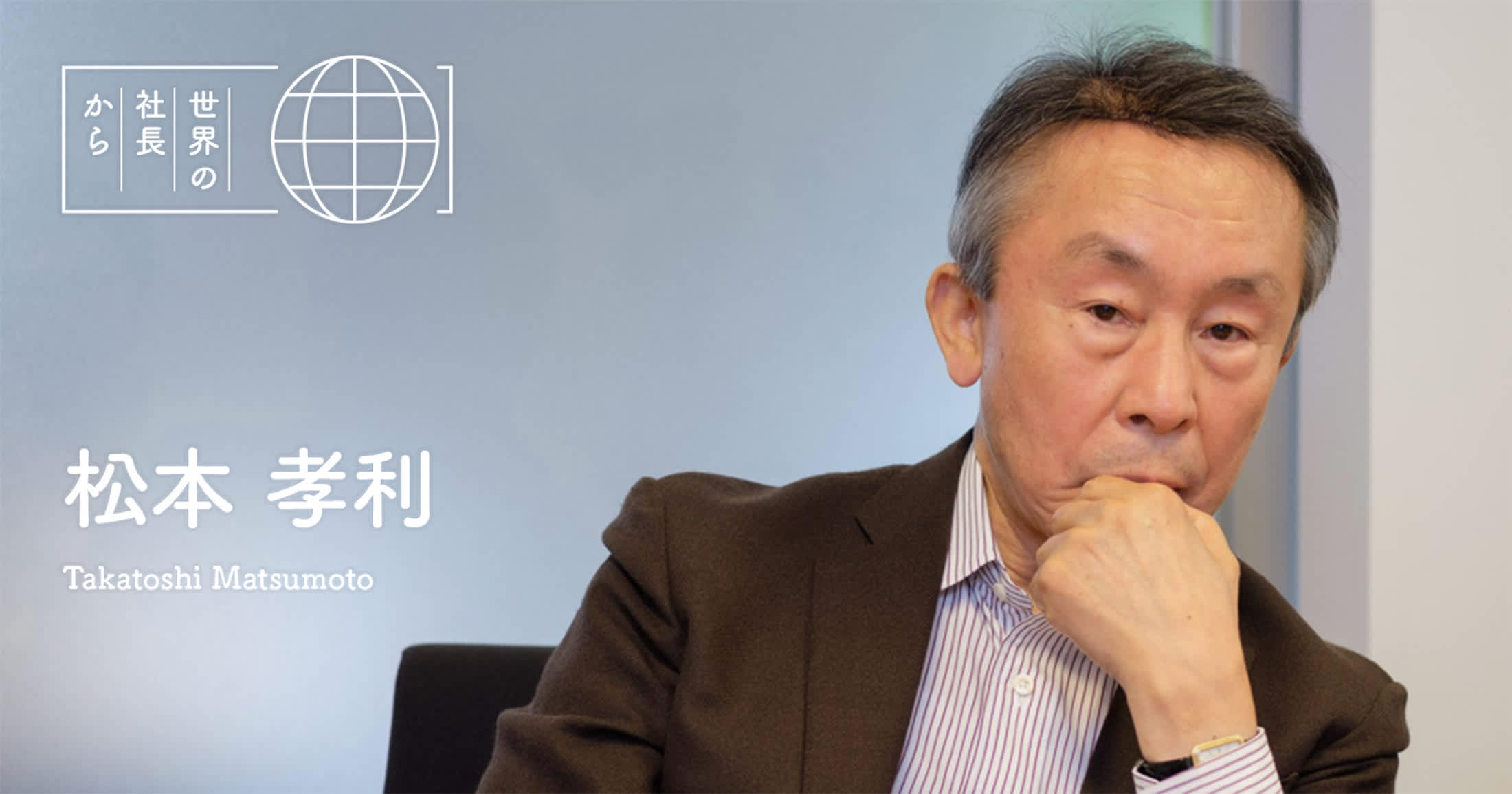サン・マイクロシステムズやシスコシステムズの日本法人を立ち上げ、日本事業の急成長を牽引した松本孝利さん。日本のインターネット黎明期から日本インターネット協会の設立に携わり、マーケット創出に取り組まれるなど、コンピュータ業界の発展と共にキャリアを歩んでこられた松本さんにお話を伺いました。
松本孝利(まつもと たかとし)
日本サンマイクロシステムズ(株)、日本シスコシステムズ(株)等をそれぞれ設立し、同時に代表取締役社長就任。 シスコシステムズでは米国本社のアジア担当副社長、日本法人会長を歴任。 その後、慶應義塾大学大学院、政策・メディア研究科教授(~2002年9月)。 法政大学ビジネススクール客員教授(~2012年)、法政大学理工学部教授(~2012年)、法政大学理事(~2008年)、法政大学名誉博士(2001年)
(ライター:福田滉平)
社長のスケーラビリティが企業の成長を決める
朝倉祐介(シニフィアン共同代表。以下、朝倉):他の国と比べると、日本の株式市場は比較的早いタイミングで会社が上場できるというのが特徴ですが、だからこそ、上場を契機にしてより成長するスタートアップが増えてこないと、スタートアップの取り組み自体がなかなか社会からの信任を得ることができないのではないかと思っています。こうした問題意識から、上場後、どのようにすれば日本のスタートアップが成長を持続できるのかということを考えています。 松本さんは1986年からサン・マイクロシステムズの日本法人社長を務められ、1992年にシスコの日本法人社長に就任されてからはアジア担当副社長まで経験されました。両社ともに、当初は小さな会社だったわけですが、グローバルでトップクラスにまで伸びるスタートアップと、そうでないスタートアップの間には、どういった違いがあるとお考えですか?
松本孝利氏(以下、松本):組織のスケーラビリティ(成長余地)は、その組織のリーダーのスケール(度量の大きさ)に依存するということです。だから、スケールの小さい社長の会社は、ビジネスモデルのスケーラビリティが大きくても、小さくまとまってしまう。

たとえば、シスコの日本法人は92年に売上ゼロのところからスタートして、1年目に700万ドル、2年目に3000万ドル、次の年は4000万ドル、6000万ドルと成長させ、ジョイント・ベンチャーをやって5億ドルまで伸びたんです。その時に強く思ったのは、上場した後に会社が伸びるかどうかは、誰が社長かで大きく左右されるということ。そして、日本にはそうしたスケールをもった人が少ないんじゃないかと思います。 上場後にさらに会社を伸ばすためには、今まで以上のリスクを取らないといけないのに、そうしたリスクを取るよりまず安定を求める社長が多いのだと思います。
時価総額トップ10が20年変わらない日本
朝倉:今の日本でスケーラビリティをもった社長というと、松本さんは誰を思い浮かべますか?
松本:ソフトバンクの孫正義社長です。彼のスケールは本当に大きいし、しかも年々成長していると思います。ソフトバンクは、ベンチャー企業として初めて日本の株式時価総額の10位以内に入っています。こういう起業家が、もう少し増えてほしいですね。一方で、アメリカはまさにITベンチャーが経済を引っ張っています。僕は90年代から、日本とアメリカの株式時価総額ランキングのトップ10を比べて見続けていますけど、アメリカの顔ぶれがガラッと変わったのに対し、日本はほとんど変わってない。
村上 誠典(シニフィアン共同代表):自動車、銀行、キャリアが中心で、少し変わったところでキーエンスですよね。
松本:日本トップのトヨタ自動車でも、アメリカの時価総額ランキングで見ればシスコの少し下ですからね。残念だと思いますよね。
サンでの急成長をシスコで再現
朝倉:松本さんは、サン・マイクロシステムズの日本法人の社長として同社の急成長を遂げられた後、シスコでも圧倒的な成長を牽引されました。
松本:僕は世界のコンピュータの夜明けから、テクノロジーが発展して、インターネットが普及するまでをコンピュータ業界で仕事をしてきました。幸運なことに、最も面白い時代を生きてきたと思っています。 サン・マイクロシステムズで成功したときには、親しい友達から「お前は運がいい」と言われたんです。その時は悔しかったのですが、同時に、自分の実力に自信がなかったのも事実です。だから、もう一度会社を立ち上げてサン・マイクロより大きく伸ばせたら、それは自分の実力だ、という気持ちが本音ではありました。そこで、シスコの立ち上げに挑戦したのです。 加えて、僕の実力は当時、売上500~600億円ぐらいまでだろうから、それ以上の規模になったら、相応の能力をもった別の人材に任せるべきだとも思っていました。ただし、自分の能力がどこまであるのか試したいという気持ちもあった。結局、日本シスコは9年目で1000億円を超えて嬉しかったですが、同時に今度こそ能力の限界と思い退任(退職)しました。

アメリカで見つけた、自分の成長機会
朝倉:松本さんは、ご自身のキャリアをNEC(日本電気)からスタートされていますね。
松本:最初は大学卒業後にNECの子会社に入って、大型コンピュータNEAC2200のOSの開発をやっていたんです。でもある時、上司と上手くいかなくなって、辞めてしまいました。当時は1960年代の後半で、一回入った会社に定年まで勤めるのが世間の常識ですからね。中途採用に応募しても、新卒採用の会社を辞めて来たって言うと採用してくれない。焦りましたね。仕方がないから、外資系のコンピュータ会社に行くしかなかったんです。でも、入社してみたらこっちのほうが自由で面白かった。
朝倉:それで、DEC(ディジタル・イクイップメント株式会社。コンピュータを開発・販売していたアメリカの会社。1998年にコンパックに買収された)に入られたんですね。
松本:日本だと上司に何でも話せと言われても、実際は難しいですよね。特に上司の間違いを指摘したりはできない。でも、アメリカの会社は職位や年齢の上下に関係なく、何でも話ができました。またあの頃のDECは伸び盛りで、世界で第6位くらいのコンピュータメーカーになっていました。DECに入社してすぐに約1年間、SEとして米国本社で研修を受ける機会にも恵まれたのですが、当時のボストンでは人種差別もあり東洋人も差別されました。混雑した食堂で一つだけ空いた席を見つけて食事をし、ふと気が付くと、同じテーブルにいた白人たちがみんないなくなっていた。会社の研修で配られる資料が、なぜかいつも僕の直前で1枚足りなくなったりしましたからね。差別されることの辛さを初めて痛感しました。すごくストレスが溜まった。そういう時は、小澤征爾氏が音楽監督をされていたボストン・シンフォニーを聞きに行きました。小柄な彼が踊るように指揮するのを見に行くわけです。曲が終わると、聴衆は熱狂してスタンディングオベーションが起こる。それを見ると、スッキリしましたね。そういう時代ですよ。
朝倉:人種差別など負の側面もある一方で、それでもアメリカの企業のほうが肌にあったんですか?
松本:そうですね。やっぱりアメリカの会社にいるほうが、実力がつくなと。なぜなら、働いた時間に関係なく、結果を出さないと給料は下がるし、それが続くとクビになりますからね。この緊張感の下で働いたほうが勉強になると思ったんです。また、オープンな企業文化も僕に合っていました。
【松本孝利】伝説の経営者が語る、成長するスタートアップの条件 Vol.1